連結会計は、のれんや少数株主持分(非支配株主持分)などの計算が不得手や人が多いと思いますが、二次試験においても問われる内容です。
図解を見ながら理解を深めてもらえればと思います。
例題
甲社と乙社があり、甲社が親会社であり、貸方に乙社株式(B)を計上しています。
文章で書けば、連結会計において、甲社の乙社株式(B)と乙社の諸資本(D’)が重複する場合があるので、それを考慮しなければいけないのが連結会計の重要ポイントです。
また、甲社が乙社の株式を100%保有しているのかどうかも重要なポイントとなります。

甲社が乙社の株式を100%保有している場合
この場合は、計算は楽になり、「乙社株式=諸資本」となります。
つまり、図で表すと下記のイメージで計算をすれば連結会計が出来上がります。
連結会計で最後に計算するところは「のれん」です。
あとは、賃借対照表が一致するように「貸方の(諸負債+諸資本)−借方の諸資産」を計算するだけです。

甲社が乙社の株式をX%保有している場合(100%ではない場合)
乙社が100%子会社でない場合、乙社の諸資本から少数株主持分(非支配株主持分)を差し引いたものが、甲社の乙社株式と一致します。
つまり、図で表すと下記のイメージで計算をすれば連結会計が出来上がります。
100%子会社である場合との大きな違いは、少数株主持分を連結会計の貸方に計上する必要があることです。
この場合は、乙社の諸資本(D’)に対して、少数株主持分である(1−X)を掛けた(D’)×(1−X)となります。
こちらも、連結会計で最後に計算するところは「のれん」です。
あとは、賃借対照表が一致するように「貸方の(諸負債+諸資本+少数株主持分)−借方の諸資産」を計算するだけです。

まとめ
- 連結会計は図で覚えると機械的に計算可能
- 二次試験でも問われるので理解が大切
- 「のれん」は最後に計算
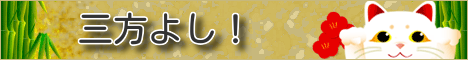
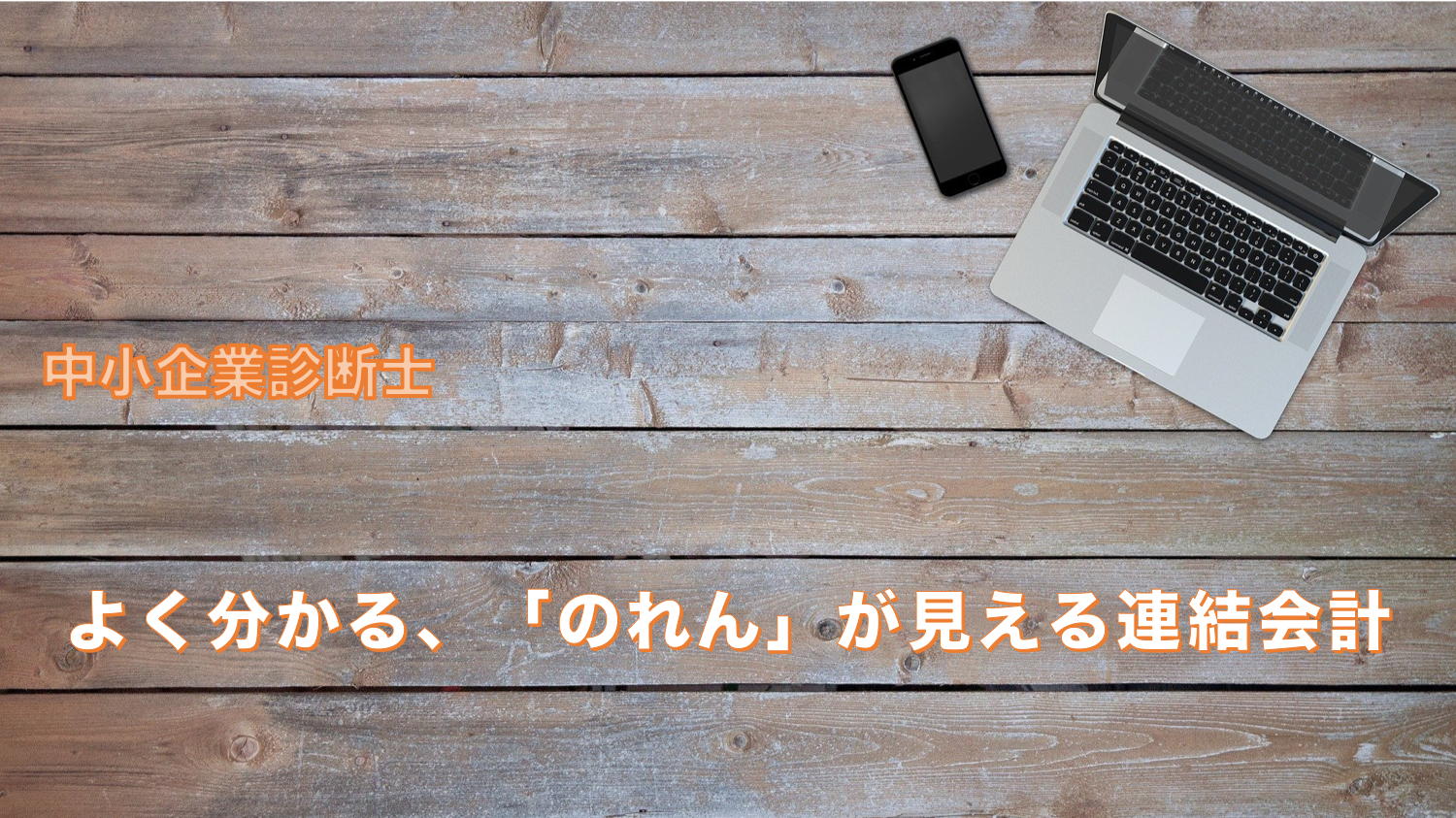


コメント